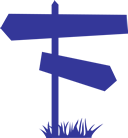叙事詩「月の夜に恋の光」『その1黄金の狐』
まちの人・ものづくりのページでは、創成東エリアで活躍するものづくり人の作品を紹介します。
****************************
叙事詩 「月の夜に恋の光」
作:中井 亮一
絵: Futaba.
何から伝えればいいのだろう?
どこまで話せばいいのだろう?
君に
暗闇から抜け出てみれば、不変の光に巡り合った。
只、あまりにも長く光を失っていた為、涙が止まらなかった。
どこにそこまでの水分が保たれていたかわからないほど、多くの涙を僕は流していた。
そう”干からびる”ほどに。
この世界に目を慣らさねばならない。
時間をかけてでも。
何かを探していた筈だから。
何かを。
時間?
時間なんてどこにあるのだ?
大型の肉食獣の、うなり声の様なものが、聞こえている。が既に、怯えは失われていたので、なるがままにまかせておいた。
”なるように、なればいい”
僕は何も恐れてはいない。と言うよりは、”恐れすら”失っていた。
その音は寸断なく”聞こえている”。
グォオオオ、グォオオオ。
これが生物なら、未知の素敵な出会いだ。
”出会いは必然である”
”そうさ答えは風が知っている”
やがてそれは、雪解けの水を運ぶ、大きな川の声だと気づいた。
それでもやはりホッとする。
”肉食動物では、なかった”ことに。
少しの安心は肌寒さを僕に知らしめた。
「寒いとこだな」僕は思った。
耳が慣れてくると、木々の揺らぎ、鳥のさえずりを僕に感じさせた。
「どこにいるのだ?」
単純な疑問が頭を覆う。
平板に聞こえる川の声。
僕は、ひたすら目が慣れるのを待つ。耳を澄まし、涙を流しながら。
その時間が、永遠なのか儚いのか?それすら、よくわからなかった。
”僕は何もわからない”
”何も覚えてはいない”
手探りで地面を触る。
土の匂いがする。草がいる。相変わらず、木々は揺れている。
だが、そこから動くことが出来ない。
僕は只白い光に包まれている。
ここに来る前、強烈な光の中に僕はいた。
身体の境界線が、ぼやける程の光の中で、僕はしばし恍惚を感じていた。
”恍惚”は、永遠かと思いきや境界線がなくなった後、光と共に去った。
そして長い間、暗闇と共にいた。
進むがままに。
瞼に差し込む光が、朱色に染まる頃、少しづつだが、目を開くことが出来た。
世界が輪郭を取り戻す。
音の正体は、やはり川だった。
大きな川だ。
視界が開けてくる。
全てが、形を”取り戻す”。
僕は、”崩れた崖”の上にいた。
ポツリと。
たった一人で。
背後に、風化した石碑のようなもの。
そこの下には、人が一人通れるかどうかの、穴があいていた。
穴を黙って見つめる。
あちら側とこちら側。
太陽は、傾いてきている。
その太陽の方向に、山並みが連なっていた。
山頂付近が白い。
山と僕の間に、木々が群生していた。
所々に、煙が立ち上っている。
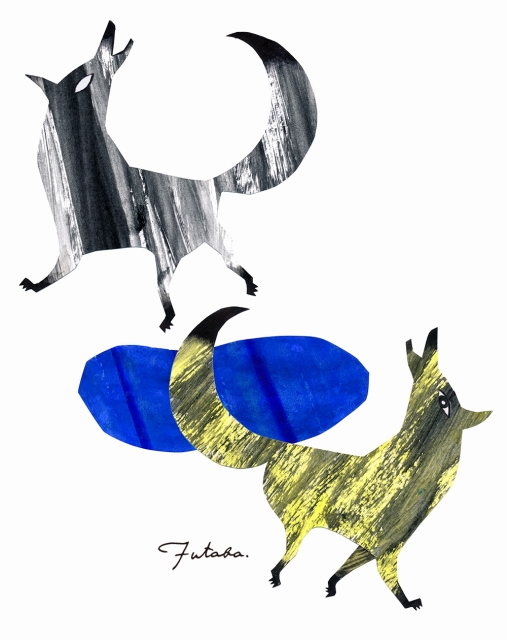
「乾いた砂を運ぶ、大きな川だよ」
声がした。
声の方向をみると、黄金の狐がいた。
狐は夕日を受けて、全ての毛が生きてるように、輝いていた。’毛”自体が生き物であるかのように。
目が合うと、狐は「やあ」と言った。
「やあ」僕も言った。
「よそ者だね」狐は見た目より、低い”いい声”だった。
「そのようだね」久しぶりに出す僕の声は、どこかぎこちない。
「おいでよ」と狐は言った。
”おいでよ”
”どこに?”
どこにでもいけばいい、答えは風が知っている。
僕は、足に力が入るか確かめながら、立ち上がった。
”ふらふら”
音がしそうだ。
立ち上がり、再びあたりを眺める。
川の向こうにとてもとても大きな月が座っていた。
満月。
そうだ満月だ。
「ピンクムーンは、特別な力があるの」彼女の言葉。
彼女?
彼女って?
4月の満月、ピンクムーン。
だけど僕は、肝心なことを、なにひとつ覚えていなかった。
つづく
****************************
本サイト「下町まちしるべ」に掲載されているコンテンツの文章、画像(写真、イラスト、動画)、音声、デザイン、データなどの著作権者は、社団法人さっぽろ下町づくり社または製作者です。コンテンツをはじめ出版物や製作物(DVDやグッズなど)は、著作権者の許諾を受けることなく、著作権法上で定められている目的(引用など)以外に、使用することはできません。